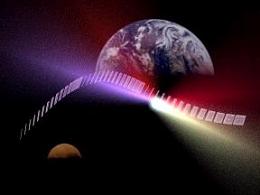第五話 サンガララの戦(3)
かくして、解放令が布告された日の晩、高原の要所に陣を敷いたインカ軍本隊の広い野営場のそこかしこからは、打楽器のリズムと明るい歌声が上がり、高所に張ったトゥパク・アマルの天幕までそれらの音が流れ込むように届いていた。
天幕を抜けて、高台から義勇兵たちの野営地を見下ろすトゥパク・アマルの傍に、老練の側近ベルムデスが近づく。
ベルムデスは、トゥパク・アマルが幼き頃から、両親をはやくに亡くした彼の父親のごとく、近しく彼に接し、見守り、また、時に養育してきた壮年の重臣である。
二人の見下ろす視線の先では、眼下の野営地のあちらこちらで焚き火を囲み、複数の義勇兵たちがそれぞれに円陣を組むようにして座り、何やら賑やかに談笑している様子が見える。
よく見ると、そこに集っている兵たちは、多くが黒人の者たちのようであった。
ベルムデスはトゥパク・アマルの方に軽く目配せしながら、温和な笑顔をつくって言う。
「どうやら、黒人の兵たちが、祝杯を上げているようですな」
トゥパク・アマルも合点がいって、「祝杯…なるほど、そうでしたか」と静かに微笑む。
「皆、トゥパク・アマル様の出された黒人奴隷解放令を喜んでいるのでしょう。
とはいえ、もう夜も遅い。
そろそろ控えさせましょうか」
問いかけるベルムデスに対して、トゥパク・アマルは野営地を見下ろしたまま、「いや、まだよいでしょう」と、変わらず静かに応える。
「あの者たちは、永きに渡り、我々インカ族の者たちよりもさらに過酷な運命を侵略者たちによって強いられて参りました。
今宵は、存分に、羽を伸ばすがよいでありましょう」
そう言って、眼下にゆるやかな視線を注ぎながら目を細めるトゥパク・アマルの横顔に、「それもそうですな」と、ベルムデスもその目元に皺を寄せて微笑んだ。
涼やかな夜風を共に浴びながら、ベルムデスはトゥパク・アマルの横顔をそっとうかがう。
(あなた様は、昔から、他の者の苦しみを、どのような末端な者のそれまでをも真に己の苦しみとし、まるっきり己のことなど忘れてしまったように、常に、この国全体のことばかりを考えていらした。
いつもそればかりで、あなた様自身の幸福を置き去りにされているのではないかと、案ずる気持ちもあったが…)
そんな思いを抱きながら改めてトゥパク・アマルを見るベルムデスの瞳の中に、恍惚たる表情のまま、瞳を輝かせ、祝杯を上げる黒人たちを見下ろすトゥパク・アマルの包み込むような眼差しが映る。
(あなた様は、歴代のインカ皇帝の、まさに生まれ変わりなのかもしれませんな。
生まれながらに、王なのか…――)
ベルムデスは、思わず、ふっと微笑む。

と、トゥパク・アマルが不意にこちらを向いた。
「何か?」
少々訝しげに問うトゥパク・アマルに、「いやいや」と、軽く手を上げてベルムデスが老練な穏やかな笑顔を返す。
「何です?」と、神妙な顔になって詰めてくるトゥパク・アマルに、「いや、本当になんでもないのです。では、私はこれで」と、笑顔で頭を下げると、ベルムデスはさっと立ち去った。
トゥパク・アマルはそんなベルムデスの後姿を見送ると、暫し、眼下に視線を戻し、流れ来るリズミカルな打楽器の音と、微かに響いてくる笑い声に、再び耳を傾けた。
一方、ビルカパサの連隊の野営地の片隅では、かの黒人青年ジェロニモが円陣の中央に座り、素焼きの筒に皮を張った手製の打楽器を勢い良く打ち鳴らしていた。
大地の奏でるような「タンタンタン」と響く野趣溢れる乾いた音は、深く、熱く、魂に染み渡る。
彼の周りには、やはり、ビルカパサの連隊に参加している黒人男性たちが、老いも若きも、おおよそ30人ほどが集(つど)っている。
ジェロニモの傍には焚き木の炎が赤々と燃え、額に汗しながら陶酔したように楽器を打ち鳴らし続ける彼の姿を、夜闇の中に浮き上がらせていた。
その周りでは、数名の黒人兵たちがジェロニモのリズムに合わせ、ひょうたんを手に楽器のごとくに打ち鳴らしている。
彼らの周りでは、それらのリズムに合わせて地を踏み鳴らして踊る者、歌う者、談笑する者がおり、そんな彼らの間から、幾度も「トゥパク様、万歳!!」の祝声が上がっては、酒よろしく水を酌み交わす姿が見られた。
その集団の方に、コイユールを引っ張るようにしながら手を引いて、マルセラが元気な足取りで近づいていく。
「ほらほら、はやく!!
私たちも一緒に祝杯を上げなきゃ!!」
マルセラの勢いにやや気圧さたような表情のコイユールに、マルセラがずいっと顔を寄せた。
「あんた、最近、なんだか元気ないんだもん。
たまには、パーッと騒がなきゃ!!
ね、さ、いくよ!!」
そう言い終るか否かの間に、マルセラは集団の中に勢いよく乗り込んでいく。
「私たちも、入れてくれない?!」
他方、今や連隊長補佐官でもあるマルセラのいきなりの乱入に、黒人兵たちの方が肝を抜かれたように、一瞬、緊張の空気が走る。
しかし、すかさずジェロニモが人懐こい笑顔を向けると、「マルセラ様、入った!!入った!!」と、明るく呼び入れた。
「そのかわり、今日は、無礼講ですから!!」と、全く物怖じしない調子で、楽器を鳴らしながら言う。
そんなジェロニモに、「そういうセリフは、普通、こっちが言うんだけど」と切り返しながら、マルセラも闊達に笑うと、円陣の中に入って座った。
その後に続くように、「こんばんは。私も、ご一緒に…」と、ややはにかんだ表情で、しかし、澄んだはっきりした声で挨拶しながら、コイユールも集団の中に加わった。

コイユールの姿を認めると、ジェロニモが近くの黒人男性へ「これ、代わってくれ!」と素早く楽器をバトンタッチして、コイユールの傍に寄ってきた。
かたやマルセラは、「わ!何それ!手製の楽器?!私にもちょっと叩かせて!」と、ジェロニモが交替した男性の方に、興味津々の顔で近づいていく。
そんなマルセラの屈託ない様子に、むしろ感心しながら見守るコイユールに、ジェロニモが水の入ったカップを持ってきて、「祝杯だ!」と笑顔で言う。
コイユールが「ありがとう」と受け取ると、「トゥパク様に乾杯!!」とジェロニモが朗らかな声を上げ、彼女のカップに自分のそれを勢いよく当てた。
それに合わせるように、二人の周りでも、「乾杯!!」の歓声が再び高らかに上がる。
コイユールは、そんな人々の恍惚とした表情を、眩しそうに見つめた。
カップを口からはずすと、ジェロニモは少しまじめな顔になって、コイユールの顔を見る。
「君の両親も、確か、ポトシの鉱山で亡くなったんだったよね」
「ええ」
「あそこには、たくさんの黒人奴隷もいたってこと、知ってる?」
「あ…、聞いたことはあるけれど」
ジェロニモは頷くと、足元にカップを置き、焚き火の方に視線を向けた。
その眼差しの鋭さに、コイユールは息を呑む。
今までの、どこかふざけた様子の彼とは、まるで別人のようにさえ見える。
「君の両親も大変だったろうけど、黒人奴隷は、インカ族の者たちよりも、もっと、ずっと過酷な条件で働かされているんだ。
全くの使い捨てサ。
働けなくなったら、殺されるんだぜ。
ひでぇ話だろ。
ま、それもそうだよな。
黒人奴隷は、『金で買われた労働力』、モノと一緒なんだから」
コイユールが絶句していると、ジェロニモはゆっくりと視線を彼女の方に戻した。
そして、微かにその瞳を震わせて、「俺の両親も、ポトシの鉱山に買われて行って、あそこで殺された」と、呟くように言う。
胸を突かれたような思いに駆られ、コイユールは殆ど無意識のうちにジェロニモの手に自分の手を添えていた。
「スペイン人を…恨んでいるの?」
自分の手に添えられたコイユールの手の方が震えているのを感じながら、ジェロニモは「恨んでない…なんて言えば、嘘になるが」と、感情を抑えた低い声で応える。
しかし、すぐに、落ち着いた、いつもの張りのある声に戻って言う。
「だけど、俺が戦いに参加したのは、奴らを恨んでるからってわけじゃあ、ないのサ。
奴らに壊された俺ら先祖や親たちの人生を…奪われた自由を、俺たち子孫の力で取り戻したいってだけだ。
あのアフリカの大地の民の誇りにかけて、ね!
それに、トゥパク・アマル様が、黒人奴隷解放令を出してくださった。
トゥパク様の統治下にある領地では、既に、解放がはじまっている。
国中の俺たち黒人の苦しみが終わる日も近いサ!!」
そう言って、「君だって参戦したのは、ただ恨みからってわけじゃあ、ないんだろ?」と、コイユールにあの出会いの日と同じ茶目っ気のあるウィンクを投げると、突然、自分の手に添えられていたコイユールの手を握り、「踊ろう!!」と立ち上がった。
思いがけぬ誘いに、コイユールが、「えっ?!」とビックリして目を瞬かせている間に、周囲からも和やかに囃(はや)し立てる歓声が上がり、一枚の彩り美しいハンカチが一人の黒人兵から投げられた。
「お嬢さん、俺らの踊りは、それを持って、だよ!!」
コイユールが呆気に取られつつもハンカチを拾っている間に、ジェロニモは自分の靴を投げ捨てるように裸足になると、「それから、俺たちは、裸足で踊る!靴、脱いで!はやく!!」と笑顔で急(せ)かす。
「えっ?えっ…」と目を丸くして驚き、戸惑いながらも、観念したようにコイユールが靴を脱ぐ。
すると、アフリカ的な、そして、躍動的ながらも低音が深く心に響く打楽器のリズムが、黒人兵たちの手によって奏でられはじめる。
さらに、それに呼応するように、歌声が湧き上がる。
その歌は、強制労働を強いられた黒人奴隷たちが想いを込めて歌い続けてきた、自由と解放の悲願の詩…――。
彼らの奏でるそのリズムは次第にスピード感を高めながらも、時に哀愁を帯び、時に優雅に、時にゆったりと、そのテンポを自在に変えていく。
マルセラはといえば、相変わらず初めての楽器を抱えながら、しかし、さすがに運動神経の良い彼女は、他の黒人たちの演奏に混ざりながら、既にそれなりにリズムを取れている。
そして、「ほら、コイユール!!私の演奏じゃ、踊れないってワケ?」と、ふざけて軽く睨んでくる。
いつの間にか、周囲に座っていた黒人兵たちも立ち上がると靴を脱ぎ捨て、男同士ながらペアになり、ハンカチを片手に、あるいは、ハンカチに加えて水瓶やひょうたんも頭上に乗せて、リズミカルに、器用に、踊りはじめる。
「ほら、あんなふうに!!」
明るい笑顔を向けるジェロニモを、コイユールは、まだ躊躇(ためら)う表情で見上げた。
そんな彼女の耳元に、ふいに顔を寄せてジェロニモが言う。
「俺たちの祖先は故郷のアフリカから引き離され、無理矢理ここに連れてこられて、終わりなき強制労働だった。
心の支えは、ずっとこの歌とリズムだけだった…のサ!
この響きは、死にかけた俺たちの魂を生き返らせてくれる。
だから、今でも生きているこのリズム、これを守って、ずっと伝えていく!
さあ、踊ろう!!」
コイユールもやっと頷くと、笑顔を返し、見よう見まねで踊りはじめる。
(そういえば私たちにも、インカの時代からずっと愛されてきた優しい音色を奏でる楽器たちが、旋律が、生きているっけ…)
コイユールは己の心にあたたかなものが満ちてくるのを感じながら、今だけは戦乱の中にあることを忘れて、大地から放たれる、躍動的で、それでいて、どこか哀愁を誘うリズムに、その身を委ねていった。